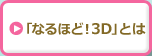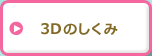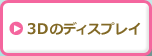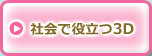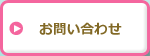第6回 「センサビスの3Dクラスルーム その5」
センサビスのウェブ上で公開されている資料「3D教育の将来(The Future of 3D Education)」から、今回は、「3Dに関する俗説」というトピックを紹介します。
3D教育における俗説の払拭
昔から、3Dのマイナスイメージを助長する俗説がいくつかあります。しかし、最近の研究により、それらには根拠がないことが示されています。ここでは、よくある俗説を紹介します。
俗説1:3Dは子どもにとって悪いものである
 3Dは子どもに有害ではないし、健康を害すこともありません。むしろ、教育において3Dは良い効果をもたらします。3D視聴により頭痛やめまいを感じる人がいるかもしれませんが、それはもしかしたら潜在的な視覚の問題を示しているかもしれません。3D視聴はそうした視覚の問題に気づくためのスクリーニング検査のような役割も果たします。
3Dは子どもに有害ではないし、健康を害すこともありません。むしろ、教育において3Dは良い効果をもたらします。3D視聴により頭痛やめまいを感じる人がいるかもしれませんが、それはもしかしたら潜在的な視覚の問題を示しているかもしれません。3D視聴はそうした視覚の問題に気づくためのスクリーニング検査のような役割も果たします。
俗説2:3D視聴は眼に悪い
その昔、3Dは眼にどのくらい影響を及ぼすのかということがメディアに多く取り上げられ、視力が悪くなるのかとか、気分を悪くするのかなどといった憶測がありました。しかし、2011年に米国オプトメトリック協会が発表したレポート「3D in the Classroom」では、3D視聴が子どもの眼に有害であるというエビデンスはないと公表されています。
俗説3:生まれたときから3Dを見ている
生まれたばかりの赤ちゃんは立体視ができません。奥行き知覚はだいたい6ヶ月くらいから始まり、2歳くらいまでに立体視ができるようになります。しかし、5,6歳まではまだ両眼視機能が完成していません。そのため、7歳以上の子どもが3Dを見られないようであれば、眼の専門家へ相談することが必要かもしれません。
俗説4:長時間の3D視聴は子どもに有害である
 一般に、長時間画面を見るようになると、どのくらい長く見ると良くないのだろうかと心配になります。3Dに限らず、パソコン画面のように何かを長い時間見続けると、かすみ目や頭痛などを引き起こします。しかし、それらの症状は一時的なものです。それに、3D教育における3D視聴は数分程度であり限定的な利用であることが多いです。
一般に、長時間画面を見るようになると、どのくらい長く見ると良くないのだろうかと心配になります。3Dに限らず、パソコン画面のように何かを長い時間見続けると、かすみ目や頭痛などを引き起こします。しかし、それらの症状は一時的なものです。それに、3D教育における3D視聴は数分程度であり限定的な利用であることが多いです。
俗説5:3Dで得られた効果は結局失われる
3D教育を実践した先生は、最初のうちは3Dに興奮しますがそれもすぐになくなり、3Dの良い効果も長く続かないのではないかと心配しました。しかし、実際にはそうではなく、子どもたちは3Dを見終わった後でも、学習内容に興味を持ち、議論や理解を続けることを望んでいました。
柴田先生のコメント
3DやVRのような新しいメディアを使おうとする際は、メディアがもたらす効果とメディアの適切な使い方の両側面から考えることが重要です。そのためには、根拠のない噂を鵜呑みにせずに、しっかりとエビデンスに基づく判断をしていくことが大切です。